2025年5月15日、FRBのジェローム・パウエル議長が第2回トーマス・ローバック研究会議で開会の辞を述べました。この会議は、故トーマス・ローバック氏の金融政策研究への貢献を称え、その研究を継続することを目的としています。パウエル議長は、FRBが5年ごとに行う金融政策の枠組み見直し(2025年レビュー)の目的や焦点、過去の経験から得られた教訓、そして今後の課題について概説しました。特に、インフレ目標、最大雇用、政策金利の運営、そして政策コミュニケーションのあり方について、過去5年間の経済状況の変化を踏まえた議論が行われることが示唆されました。
- 発言内容全文(PDF): powell20250515a.pdf
- 第2回トーマス・ローバック研究会議 詳細: Second Thomas Laubach Research Conference
- 連邦準備制度(FRB)公式サイト: www.federalreserve.gov
免責事項: この記事はYoutube動画の字幕データを基に翻訳し要約したものです。実際の会談のニュアンスや完全な文脈を反映していない可能性があります。詳細は元動画をご確認ください。タイムスタンプはおおよその目安です。
- [00:00] 開会の挨拶と会議の趣旨
- [00:23] 2025年レビューの構成要素
- [00:45] 今回のレビューの焦点:戦略的枠組みとコミュニケーションツール
- [01:12] コンセンサス・ステートメントの歴史と重要性
- [01:42] 経済構造の変化と金融政策の進化の必要性
- [02:05] 定期的な枠組み見直しの意義
- [02:33] 5年ごとのレビューの妥当性
- [02:51] 前回のレビュー時の経済状況:低金利・低成長・低インフレ
- [03:19] 金融危機後の緩やかな利上げとパンデミック前の状況
- [03:44] 低金利下限への回帰懸念
- [04:04] 低金利下での懸念とインフレ目標未達への対応策
- [04:29] インフレ率が2%を下回った場合の対応
- [04:49] 最大雇用に関する方針変更:「乖離」から「不足」へ
- [05:15] 労働市場の逼迫と物価安定の両立の可能性
- [05:34] パンデミック前の低失業率と低インフレ
- [05:59] パンデミック前の経済状況と枠組み変更の背景
- [06:17] 意図的なインフレオーバーシュート政策の実際とパンデミック後のインフレ
- [06:35] 伝統的インフレ目標への回帰と当初のインフレ予測
- [06:58] インフレ高進への対応とディスインフレの成果
- [07:26] 2020年以降の経済環境の変化とレビューへの反映
- [07:47] 実質金利上昇の背景と供給ショックの可能性
- [08:12] 低金利リスクへの備えとインフレ期待のアンカリングの重要性
- [08:32] グレート・モデレーションと固定されたインフレ期待の役割
- [08:51] 近年のディスインフレとインフレ期待の固定
- [09:13] 現在のレビューにおける議論の焦点:2020年の変更点の再検討
- [09:31] 「不足」アプローチと平均インフレ目標の再検討
- [09:49] 平均インフレ目標の再検討と新たなコンセンサス・ステートメント
- [10:13] コミュニケーションの重要性と改善の余地
- [10:36] 不確実性に関する理解促進とコミュニケーションの課題
- [10:59] 結びの言葉
[00:00] 開会の挨拶と会議の趣旨
皆様、ようこそお越しくださいました。ご参加いただきありがとうございます。トーマス・ローバック氏の研究と、FOMCへの広範な貢献は、我々が金融政策をより良く理解する助けとなりました。今日、彼の名を冠してこの研究が継続されることは、誠に意義深いことです。論文の執筆者の皆様、討論者の皆様、そしてパネル参加者の皆様に感謝申し上げます。また、この会議を企画してくださったトレバーとそのチームにも感謝いたします。
[00:23] 2025年レビューの構成要素
我々が一堂に会するためには、多大な努力が払われました。前回のレビューと同様に、2025年のレビューは3つの主要な要素で構成されています。この会議、全国の連邦準備銀行で開催される「Fed Listens」イベント、そして一連のFOMC会合におけるスタッフ分析に裏打ちされた政策立案者による議論と審議です。
[00:45] 今回のレビューの焦点:戦略的枠組みとコミュニケーションツール
現在のレビューでは、過去5年間の経験を踏まえ、我々の戦略的枠組みの側面を再考します。また、予測、不確実性、リスクに関する委員会の政策コミュニケーションツールの改善可能性についても検討します。2012年、FOMCは初めて金融政策の枠組みを「長期目標と金融政策戦略に関する声明」(コンセンサス・ステートメントと呼んでいます)という文書にまとめました。
[01:12] コンセンサス・ステートメントの歴史と重要性
冒頭の段落の文言は一度も変更されておらず、議会から負託された使命を全うし、我々が何を行い、なぜそれを行うのかを明確に説明するという我々のコミットメントを明確に示しています。その明確さが不確実性を低減し、我々の政策の有効性を高め、透明性と説明責任を強化します。ベン・バーナンキ議長(当時)は、その最初のコンセンサス・ステートメントの作成を通じて委員会を導き、2%のインフレ目標を採用し、議会から与えられた二大責務を達成するための我々のアプローチを概説しました。
[01:42] 経済構造の変化と金融政策の進化の必要性
その文書に示された枠組みは、柔軟なインフレ目標を採用する中央銀行のベストプラクティスと広範に一致していました。経済の構造は時間とともに進化し、金融政策担当者の戦略、ツール、コミュニケーションもそれに伴って進化する必要があります。世界大恐慌が提示した課題は、大インフレ時代やグレート・モデレーション時代の課題とは異なり、それらはまた今日我々が直面している課題とも異なります。
[02:05] 定期的な枠組み見直しの意義
枠組みは広範な状況に対して頑健であるべきですが、経済とその理解が進化するにつれて定期的に更新される必要もあります。2012年から2018年にかけて、FOMCは毎年1月の会合で、ほとんどの年に実質的な変更なしにコンセンサス・ステートメントを再確認することを議決しました。2019年に、我々はその慣行を変更し、史上初の公開レビューを実施し、約5年ごとにそのようなレビューを繰り返すと述べました。
[02:33] 5年ごとのレビューの妥当性
5年というペースに何か特別な意味があるわけではありません。我々は、その頻度が経済の構造的特徴を再評価し、我々の枠組みのパフォーマンスについて一般市民、実務家、学者と関わるのに適切であると考えています。我々のグローバルな同業他社のいくつか(他国の中央銀行)も、枠組みレビューに対して同様のアプローチを採用しています。
[02:51] 前回のレビュー時の経済状況:低金利・低成長・低インフレ
前回のレビューの時点では、我々は約10年間、低金利、低成長、低インフレ、そして非常にフラットなフィリップス曲線によって特徴づけられる、実効金利下限に近い「ニューノーマル」の状況にありました。もしその時代を一つの統計で捉えるならば、2008年後半の世界金融危機の発生後、政策金利が7年間もの長きにわたり実効金利下限に張り付いていたということでしょう。
[03:19] 金融危機後の緩やかな利上げとパンデミック前の状況
2015年12月の利上げ開始後、我々は3年間にわたり非常に緩やかにしか政策金利を引き上げることができず、ピークはわずか2.4%でした。その7ヶ月後には利下げを開始し、2019年後半には金利を1.6%とし、数ヶ月後にパンデミックが発生した際もその水準でした。他の主要先進国の政策金利はさらに低く、多くの場合ゼロを下回っていました。
[03:44] 低金利下限への回帰懸念
そして、そのような全ての経済において、インフレ率は定期的に目標を下回っていました。当時の感覚としては、経済が次にたとえ緩やかな景気後退を経験したとしても、我々はすぐに実効金利下限に戻り、おそらく再び長期間そこに留まるだろうというものでした。金融危機後の10年間は、それがもたらしうる苦痛を示していました。
[04:04] 低金利下での懸念とインフレ目標未達への対応策
弱い経済ではインフレ率が低下し、名目金利がゼロに固定されるため実質金利が上昇する可能性が高いでしょう。実質金利の上昇は、雇用の伸びをさらに圧迫し、インフレとインフレ期待への下方圧力を強めることになります。これらの懸念を反映し、我々はインフレ目標からの持続的な未達を補うための政策を採用しました。これは、実効金利下限に関連するリスクに関する広範な文献で一般的だったアプローチです。
[04:29] インフレ率が2%を下回った場合の対応
実効金利下限への近接による雇用とインフレへの下方リスク、そして長期的なインフレ期待を2%に固定する必要性を考慮し、我々は、インフレ率が持続的に2%を下回って推移した期間の後には、しばらくの間、2%を適度に上回るインフレ率を達成することを目指す可能性が高いと述べました。
[04:49] 最大雇用に関する方針変更:「乖離」から「不足」へ
また、政策決定は最大雇用からの「乖離(deviations)」ではなく「不足(shortfalls)」の評価に基づいて行われると結論付けました。「不足」への変更は、恒久的に先制的な引き締めを行うことや、労働市場の逼迫を無視することを約束するものではありませんでした。むしろ、それは、委員会が放置すれば望ましくないインフレ圧力につながると考えない限り、見かけ上の労働市場の逼迫だけでは政策対応の引き金にはならないことを示唆するものでした。
[05:15] 労働市場の逼迫と物価安定の両立の可能性
この変更は、低く安定したインフレの中で歴史的に低い失業率を特徴とする長期の景気拡大の経験を反映したものであり、最大雇用レベルを慎重に探る政策アプローチが、物価の安定を損なうことなく強力な労働市場の恩恵をもたらしうることを示唆していました。
[05:34] パンデミック前の低失業率と低インフレ
例えば、パンデミック直前の数年間は、失業率は数十年来の低水準でしたが、インフレ率は2%を下回っていました。2019年12月までには、長期的な失業率の推定値は大幅に低下していました。「不足」の採用は、低インフレと低失業率の組み合わせが、必ずしも金融政策にとって不利なトレードオフをもたらすわけではないことを認めたものでした。
[05:59] パンデミック前の経済状況と枠組み変更の背景
我々を実効金利下限に近づけ、コンセンサス・ステートメントの変更を促した経済状況は、少なくとも次回の5年ごとのレビューまでは長期間持続する可能性が高い、緩やかに進行する世界的な要因に根差していると考えられていました。そして、パンデミックが介在しなければ、おそらくそうだったでしょう。
[06:17] 意図的なインフレオーバーシュート政策の実際とパンデミック後のインフレ
意図的な緩やかなオーバーシュートという考えは、我々の政策議論とは無関係であり、今日に至るまでその状態が続いています。我々がコンセンサス・ステートメントの変更を発表した数ヶ月後に到来した世界的なインフレは、意図的なものでも緩やかなものでもありませんでした。そして、私は2021年12月にそのことを公に認めました。
[06:35] 伝統的インフレ目標への回帰と当初のインフレ予測
我々は枠組みの残りの部分に立ち返り、それは2021年末まで伝統的なインフレ目標を求めるものでした。FOMC参加者は、2022年にはインフレがかなり急速に沈静化し、政策金利の引き上げも緩やかなものにとどまる可能性が高いと予測し続けました。その予測は、異なる枠組みを持つ他の中央銀行や、大多数の予測担当者と一致していました。
[06:58] インフレ高進への対応とディスインフレの成果
証拠がそれとは異なることを示したとき、我々は16ヶ月の間に525ベーシスポイントの利上げを行いました。最新のデータによると、4月の12ヶ月PCEインフレ率は2.2%で、2022年のピーク7.2%をはるかに下回っています。そして、この部屋の皆さんがご存知のように、歓迎すべき歴史的にも異例な結果として、このディスインフレは、インフレ抑制のための利上げキャンペーンにしばしば伴う失業率の急上昇なしに達成されました。
[07:26] 2020年以降の経済環境の変化とレビューへの反映
2020年以降、経済環境は著しく変化しており、我々のレビューはそれらの変化に対する評価を反映したものとなるでしょう。長期金利は現在かなり高くなっており、これは主に長期的なインフレ期待の安定性を考えると実質金利によって牽引されています。経済予測サマリー(SEP)に含まれるものを含め、長期的な政策金利水準の多くの推定値が上昇しています。
[07:47] 実質金利上昇の背景と供給ショックの可能性
実質金利の上昇はまた、2010年代の危機間の期間よりも、今後インフレがより不安定になる可能性を反映しているかもしれません。我々は、より頻繁で、潜在的により持続的な供給ショックの時代に入りつつある可能性があり、これは経済と中央銀行にとって困難な課題です。我々の政策金利は現在、実効金利下限を十分に上回っていますが、ここ数十年間、経済が不況に陥った際には約500ベーシスポイントの利下げを行ってきました。
[08:12] 低金利リスクへの備えとインフレ期待のアンカリングの重要性
実効金利下限に陥ることはもはや基本シナリオではありませんが、枠組みがそのリスクに対処し続けることは賢明です。枠組みは進化しなければなりませんが、その一部の要素は時代を超越したものです。政策立案者は、大インフレ時代から、インフレ期待を適切に低い水準に固定することが不可欠であるという明確な理解を得てきました。
[08:32] グレート・モデレーションと固定されたインフレ期待の役割
グレート・モデレーションの間、十分に固定されたインフレ期待は、不安定なインフレを引き起こすリスクなしに雇用への政策支援を提供することを可能にしました。大インフレ時代以降、米国経済は記録上4つの最長景気拡大のうち3つを経験しました。固定された期待は、これらの拡大を促進する上で重要な役割を果たしました。
[08:51] 近年のディスインフレとインフレ期待の固定
より最近では、そのアンカーがなければ、失業率の急上昇なしに約5パーセントポイントのディスインフレを達成することは不可能だったでしょう。長期的なインフレ期待を固定し続けることは、2012年の枠組みで2%目標を確立する原動力でした。そのアンカーを維持することは、2020年の変更の背後にある主要な考慮事項でした。
[09:13] 現在のレビューにおける議論の焦点:2020年の変更点の再検討
固定された期待は我々が行う全てのことに不可欠であり、我々は今日においても2%目標に完全にコミットしています。現在のレビューでは、委員会は過去5年間の経験から何を学んだかについての議論に取り組んでいます。我々は、今後数ヶ月でコンセンサス・ステートメントへの具体的な変更の検討を完了する予定です。
[09:31] 「不足」アプローチと平均インフレ目標の再検討
我々は、経済について学んだことと、それらの変更が一般市民によってどのように解釈されたかを反映する、慎重かつ重要な更新を検討するにあたり、2020年の変更に特に注意を払っています。これまでの議論では、参加者は「不足(shortfalls)」に関する文言を再考することが適切であるとの考えを示しています。
[09:49] 平均インフレ目標の再検討と新たなコンセンサス・ステートメント
そして先週の会合では、平均インフレ目標についても同様の見解でした。我々は、新しいコンセンサス・ステートメントが広範な経済環境と動向に対して頑健であることを保証します。コンセンサス・ステートメントの改訂に加えて、我々はまた、特に予測と不確実性の役割に関して、公式な政策コミュニケーションの潜在的な強化についても検討します。
[10:13] コミュニケーションの重要性と改善の余地
2020年の枠組みと近年の政策決定の評価を見直してきた中で、共通の所見は、複雑な事象が展開する中での明確なコミュニケーションの必要性です。学者や市場参加者は一般的にFOMCのコミュニケーションを効果的であると見なしてきましたが、改善の余地は常にあります。実際、明確なコミュニケーションは、比較的穏やかな時期でさえ問題となります。
[10:36] 不確実性に関する理解促進とコミュニケーションの課題
重要な問題は、経済が一般的に直面する不確実性についてのより広範な理解をどのように育むかということです。より大きく、より頻繁な、またはより異質なショックがある期間には、効果的なコミュニケーションは、我々の経済と見通しに関する理解を取り巻く不確実性を伝えることを必要とします。我々は、今後、その側面での改善方法を検討していきます。
[10:59] 結びの言葉
それでは、最後に改めて、ご参加いただきありがとうございます。我々一同、今日皆様とご一緒し、今後2日間にわたって行われるこれらの会話を楽しみにしておりました。これらの議論は、これらの問題に関する我々の考えを広げ、深めるのに役立ち、これらのレビューの成功に不可欠です。どうもありがとうございました。

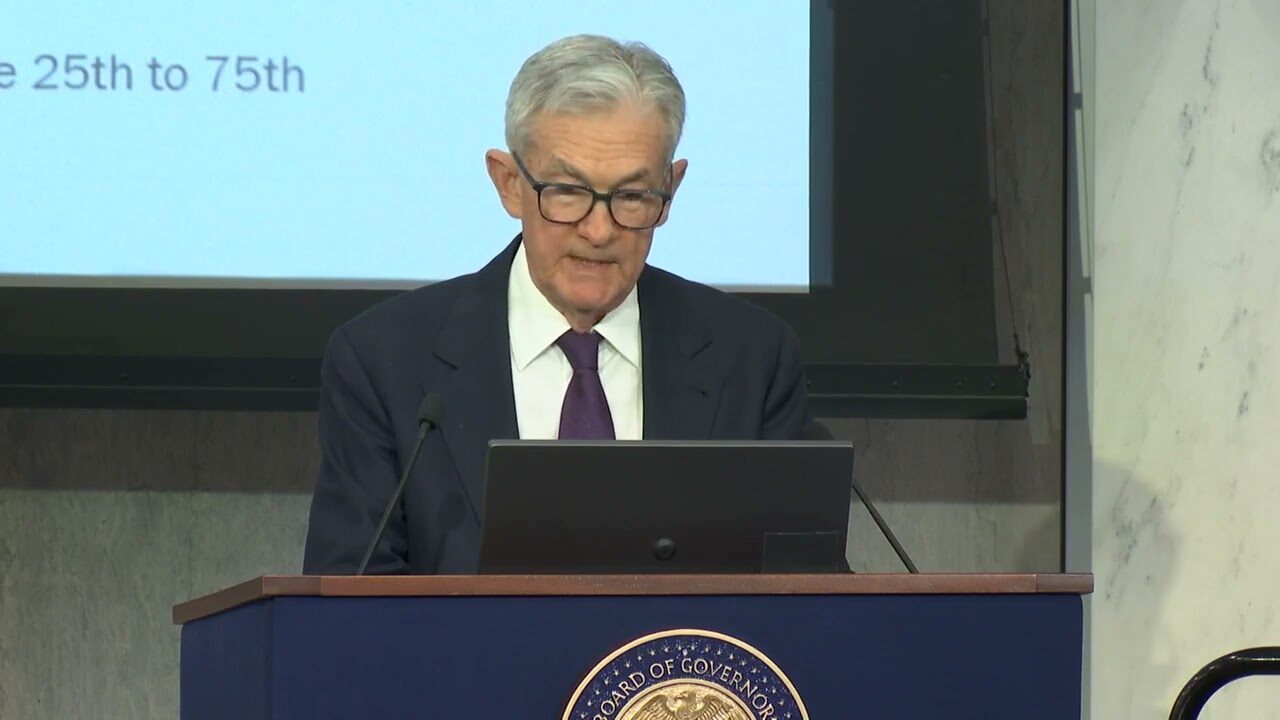


コメント